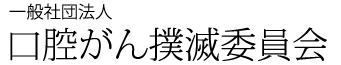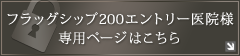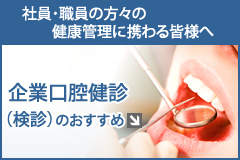我々は、この世界的に実績のあるVELscope®Vxの日本への導入展開を図るため、渡米し、メーカーのLEDデンタル社及び世界総販売代理店であるデンマット社と日本への独占輸入及び契約販売総代理契約を締結しました。
この世界的実績のあるVELscope®Vxを組み込んだ「口腔がん検診・口腔健診システム」を全国各地の一般歯科医院や歯科大学の付属病院、そして、人間ドック・健康診断機関で、簡単に受診できる仕組みを構築すべきだと考えました。
と言いますのは、VELscope®Vxだけを日本国内で医療機器として許認可を受け、歯科医院に向けて販売開始したとしても、以下の理由にて検診の普及を図ることは難しいと考えたからです。
そもそも日本国民全体は「口腔健診」意識が低い(口腔健診に行かない)。 ※図13の通り、日本の口腔健診受診率は「たった2%」と言われています。歯科先進国のスウェーデンが90%、同じく、米国が80%の受診率、と言われている中。

一般人も歯科医師も「口腔がん」に対する認識や知識が低い。
人間ドック及び健康診断を行う医療機関や健保組合においての「口腔健診」に対する意識が低い。
さらには、
一般の歯科医師は口腔がんの症例経験が少なく検診できない。
一次診断を支援してくれる仕組み(遠隔画像診断システム)がない。
怪しいと思った際に、その患者を紹介する施設(歯科大学病院口腔外科など)との連携体制が構築されていない。
健診は歯科医院にあまり報酬が残らない(ボランティア的)。
口腔がん検診を始めた結果、がんを見逃して訴訟に巻き込まれるのが怖い。
などの課題があるからです。
ゆえに、試行錯誤を重ねた結果、VELscope®Vx(当時の蛍光観察装置はVELscope®Vxのみだった)を活用して「口腔内全体を健診する仕組み」として提供することで、口腔がんの早期発見と将来口腔がんや様々な病気に繋がる可能性の要素を早期に発見し、同時に、健診後の継続通院にて早期治療(保険・自費)や口腔内クリーニングを行うこと、つまり、健診と治療という一連の流れを確立し、口腔がんの早期発見と共に、歯科医院の対価・報酬にも貢献できる仕組みを構築することを考えました。
●全国歯科医院における「口腔がん検診・口腔健診」の普及
●全国人間ドック及び健康診断機関における「口腔がん検診・口腔健診」の普及 を目指したく思います。

つまり、年齢にかかわりなく、口腔内にある問題すべてが「口腔がん」に繫がる可能性があるということなのです。
したがって、がん化する前に、定期的に口腔内を健診し、その要素を摘み取り治療を行うことが口腔がんを防ぐことになります。
また、米国では「HPV(ウィルス)」による10代の口腔がん罹患者が増加しています。HPVとは、子宮頸がんを発症させるウィルスですが、性行為(オーラルSEX)の低年齢化によってHPVが口腔に入り、結果、口腔がんを発症させる症例が増加しています。日本ではまだまだその症例は少ないですが、最近、増加傾向になってきています。

一般的には、口腔がんになるまでには5~10年くらいの期間がかかりますので、それまでに将来口腔がんになる要素を治療により摘んでしまえば良い訳です。(図14)
例えば、歯列が揃っておらず内側に出っ張っている歯があることにより、日常的にその歯は舌のその部分だけに接触を繰り返すことにより、その部分の皮膚にストレスが積み重なり異形成化し(前がん状態になり)、やがてはがん化する可能性があります。しかし、それを早期に歯列矯正し、がん化する可能性を取り去る治療を行えば予防できます。
あるいは、口内炎ができやすい体質を改善する(口内炎からがん化する)、入れ歯が合わずに恒常的に痛みを感じている部分を改善し、その部分ががん化するのを防ぐ、また、がん化することはなくても、金属(特にアマルガムなど)の詰め物により原因不明の体調不良を引き起こす要素を取り除くなど、様々な病気の元となる歯周病やう蝕(虫歯)を治療し、且つ、継続予防することにより全身の病気や成人病の可能性を小さくするなど、口腔健診後の口腔内全体に渡る治療を継続して実施することが、口腔ケアを行う定期通院患者数を増加させることにつながり、結果、患者も歯科医院もwin&winの関係を構築できるようにすれば良いのでは?と考えました。
各々の利点
- ・口腔がんの早期発見
- ・口腔内問題の早期発見(全身予防)
- ・健診目的による患者の増加
- ・健診+口腔内治療による医療収入の向上
- ・早期発見治療による死亡率の低減
- ・歯科医院との連携強化
- ・企業を中心とした口腔がん、口腔健診実施による収益向上
- ・口腔健診の取込による健診収入向上
- ・「予防」という観点での医科歯科連携
- ・医療費の削減
(口腔がん治療費の削減&予防による削減)
それを、図15のような一連のシステムにつなぎあわせ、且つ、受診者に対し診断書を発行する仕組みとして、以下のような「口腔がん検診・口腔健診システム」として企画開発しました。
 ]
]